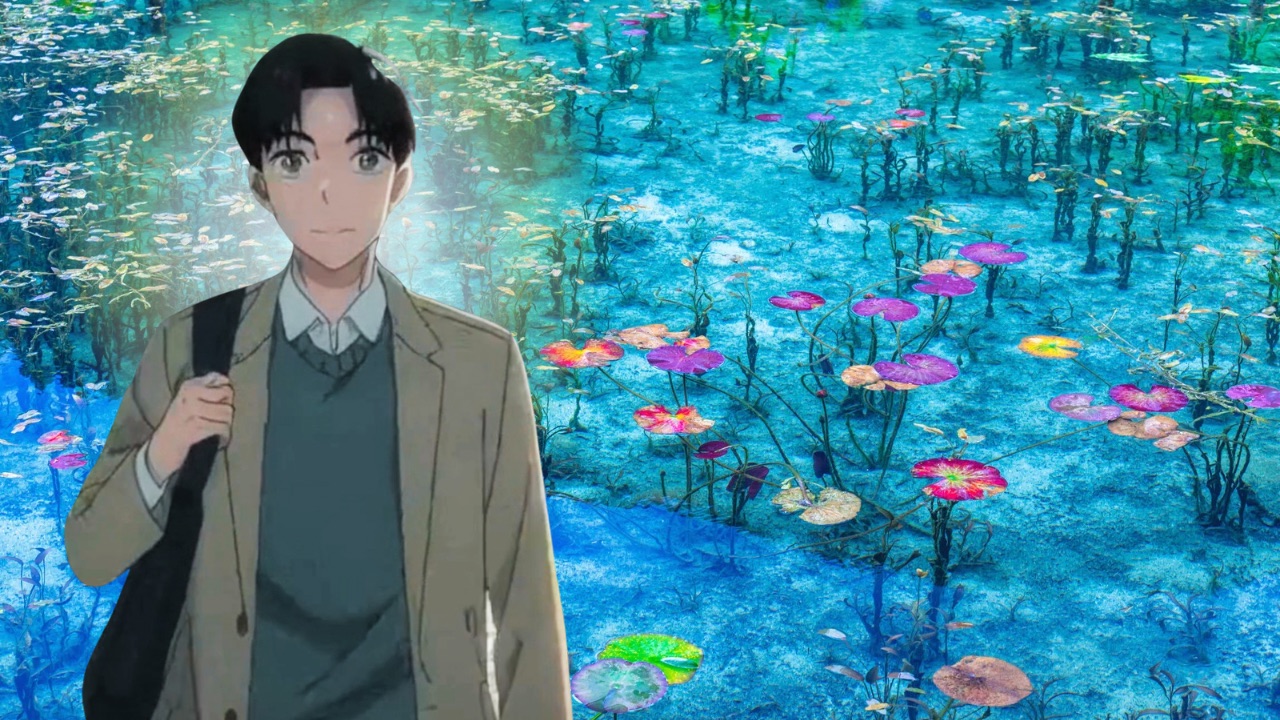


数字の心に触れた男
数字と効率の世界で生きてきた一人の銀行員が、
再開発案件をきっかけに、「お金」と「豊かさ」の本質に揺さぶられていく。
これは、人生の意味と本当の豊かさを思い出していく、意識の変容の物語。
プロローグ
都市銀行のオフィスは、冷たい静けさに満ちていた。
親切に接する中にも、心の感情を切り離し、ただ数字と効率だけが求められる空間。
法人融資部に勤める彼は、正確で、速く、ミスのない仕事ぶりで周囲から一目置かれていた。
感情を表に出すこともなく、無駄を嫌い、すべてを合理的に処理する日々。
それは、まるで心を眠らせたまま進むような、静かな機械のような働き方だった。
疑問もなく、迷いもなく――
ただ、与えられたレールを完璧に走り続けていた。
そんな彼に、ある日届いたひとつの案件。
それは、母の故郷である地方の、再開発プロジェクトだった。
かつて夏休みを過ごしていた、美しい自然が残る土地。
彼の心の奥に、やわらかく残っていた、遠い記憶の風景だった。
そして、それは――
数字の世界だけを見て生きてきた彼の中に、
初めて、問いの種を落とすことになる。
ここから、ひとりの銀行員の
世界の“本当の姿”に気づいていく、
「変容の物語」が始まっていく。
第1章 数字の向こうに見えたもの
再開発案件の資料が届いたのは、いつものように静かな午後だった。
複数の部署にまたがる大型案件のため、法人融資部にも詳細が共有された。
地方都市の駅前整備計画。新しい商業施設、道路拡張、観光誘致のインフラ整備。
彼は、当たり前のように資料を開き、数字の海に没入した。
売上予測、投資回収率、リスク評価……どれも標準的で、不自然な点はなかった。
ただ一つを除いて。
計画地の名前を目にしたとき――
彼の手が、一瞬止まった。
「……この地名……」
それは、彼の母が生まれ育った町だった。
彼が子どもの頃、いつも夏休みを過ごしていた場所。
祖父母の家の近くには、小さな川が流れていた。
従兄弟とカブトムシを追いかけた林、夕暮れに鳴いていたカエルの声、祖母の作る甘い梅ジュース。
あの風景が、再開発される。
予算案の中には、「老朽施設の撤去」や「緑地の一部縮小」といった文言が並んでいた。
実際には、あの森も、川も、すべて整地され、コンクリートの舗装道路へと変わっていく。
資料の中で語られる“地域活性化”という言葉が、妙に空虚に感じられた。
彼は、再び書類に目を落としながら、心の中で自問していた。
「これは……誰のための“開発”なんだ?」
いつもなら、気に留めることすらなかった疑問。
けれど今回は、数字の向こうに“自分の記憶”が重なった。
合理性の影で削られていくものが、はじめて「他人ごと」ではなかった。
その夜。
彼は久しぶりに、母に電話をかけた。
「……あの町、再開発されるらしいよ。駅前のあたり、一帯。」
電話の向こうで、母が少し沈黙した。
「そうなの……あの辺り、みんな年取ってしまってね。もう誰も声を上げられないのよ。」
一瞬、胸の奥に冷たい痛みが走った。
過疎化、老朽化、経済合理性。
現代の常識として受け入れてきた言葉の裏にある、静かな諦め。
かつて自分が遊び、心を育んだあの風景は、もう誰の“守りたい場所”でもなくなっていた。
そして、その仕組みに、自分が加担している。
彼はその夜、資料を再び開きながら、初めて言葉にできない違和感を抱いた。
開発とは何か。
豊かさとは何か。
正しい経済とは、誰の視点で語られるものなのか。
彼の中に、静かに“問い”が芽生えはじめていた。
第二章 静かに、扉が開く
あの案件を境に、彼の中で何かが変わり始めていた。
外側の日常は何も変わらない。
朝の満員電車。コーヒーの香り。会議。プレゼン。数字。数字。数字。
けれど、そのすべての裏に、淡い違和感が差し込んでいた。
仕事帰り、たまたま立ち寄った書店で、一冊の薄い本が目にとまった。
『愛の経済のための本 ― 世界平和への道 ―』
著者は無名だった。出版元も聞いたことがない。
けれどなぜか、その本だけが妙に静かに、彼の目の前に存在していた。
その夜、自宅のソファに腰を下ろし、ページをめくり始めた。
難しい言葉は使われていなかった。けれど、書かれていたのは、これまで誰からも聞いたことのない内容だった。
「お金は、“恐れ”を媒介として、人の心を支配する道具となってしまった。
お金を、人を助け合いへと導く“愛のエネルギー”に変換する必要がある。」
思わず、ページをめくる手が止まらなくなった。
「人間は、“お金”という幻想の神を信じ、その神のために自分自身を犠牲にしていることに気づかねばならない。」
陰謀論のように受け取られそうな内容も含まれていた。
彼はその手の話には懐疑的だったし、あくまで冷静な分析を好む人間だった。
だが、この本には、どこか“知性とやさしさ”があった。
たとえば、こんな言葉――
「真の経済とは、“分かち合い”の循環である。
平和が約260年間続いた江戸時代の村落経済には、貨幣を補助としながら、自然と共生する叡智があった。
必要な分だけを受け取り、余ったものは隣人に渡す。
それが、本来の“豊かさ”の循環だった。」
それは、彼がかつて祖父母の家で見た、食べ物を分け合う近所の人々の姿と重なった。
あれは、単なる田舎の風習だと思っていた。
だがそこには、現代が失ってしまった「生きる経済」があったのかもしれない。
彼の中で、何かが静かに動き出した。
いま自分が関わっている“経済”は――
本当に人を幸せにしているのか?
森を壊し、静かな町を変えてまで、誰が得をしているのか?
彼の仕事では、数字は絶対だった。
売上、利益、利回り、回収率、リスク評価。
だが、そのどれもが「命」や「つながり」といった、目に見えないものを評価していなかった。
この本は、そうした“見えないもの”を、経済の中心に据えていた。
彼は驚きとともに、自分の心の奥底が――
「ほっとしている」のを感じた。
それはまるで、ずっと忘れていた何かを、思い出したような感覚だった。
翌朝、彼はふと自分の出勤する姿を鏡で見つめた。
よく仕立てられたスーツ、ネクタイ、革靴。
どれも違和感はない。だが、心だけが、少しだけ外に立っているようだった。
「もしかして、自分は……何か大事なものを見失っているのかもしれない」
そんな言葉が、心のどこかから浮かんできた。
そして、彼の中にあったもうひとつの問いが、静かに形を取り始めていた。
「お金って、いったい何だ?」
第3章 静かな衝突
日々の仕事に戻っても、彼の意識はもう、かつてのようには動かなかった。
いや、動けなかった。
取引先企業の財務諸表を前にしても、数字の背後に「人の暮らし」や「自然の景色」が浮かんでくる。
──この“利益”の中に、何が失われているのだろう。
そんな考えが、ふと湧いては消え、消えてはまた戻ってくる。
ある日、彼は担当していた建設会社の社長から、次のような報告を受けた。
「例の山の開発、順調です。少し予定より伐採が進んでますが、道路も広くなるし、観光地としても期待できますよ」
“伐採が進んでます”──
その言葉が、胸の奥に小さな棘のように刺さった。
開発されるのは、あの場所だ。
父母と手をつないで歩いた小道。
蝉の声が響いていた、祖母の庭先。
夏の午後、従兄弟と川辺で空を見上げた記憶。
親切だった近所の人たち。
それらが、まるで“なかったこと”のように、消されようとしていた。
だが、彼の仕事は「それを実現させる側」だった。
表情を変えずに書類を受け取り、融資の評価を進める。
条件に沿っていれば、実行に移す。
それが“仕事”だった。
その日、帰りの電車の窓に映る自分の顔が、どこか遠く感じた。
“誰も悪くない”
──それは分かっていた。
建設会社の社長も、プロジェクトの担当者も、地域の自治体も、それぞれの「善意」で動いていた。
地域の活性化、雇用の創出、利便性の向上。
だが、その裏で、静かな森が失われ、野生の動物たちの居場所がなくなり、記憶の風景がひとつ、またひとつと消えていく。
そして、その決定に、自分の押した“承認”の印がある。
その夜、彼は眠れなかった。
窓の外に広がる都会の灯りが、妙にまぶしかった。
「なぜこんな仕組みが当たり前になっているのか?」
自分が今まで信じてきた“経済”という仕組みの裏側に、ほんのわずかでも「問い」が生まれたとき、すべてが揺らぎ始めた。
翌朝、机に置かれた案件の山を見つめながら、彼はふと、ある思いにとらわれた。
「自分は、人を幸せにしているのだろうか?」
利益を上げ、融資を通し、会社を動かし、経済を支える。
それは“成功”と呼ばれる仕事だった。
社会的には“幸せ”と評価される。
だが、そのどこに「心」があるのか、本当の「幸せ」なのか、自分自身にも答えられなかった。
世界は、正しさであふれていた。
だが、その正しさの中で、誰かが泣いていた。
そして、自分もまた、その“仕組み”の一部だった。
小さな疑問が、静かな怒りへと変わり始めていた。
混乱が生まれ、感情がざわめき、心の奥から、何かが崩れていく音がした。
それは、理性でつくりあげてきた“完璧な自分”という仮面が、少しずつ剥がれていく音だった。
第4章 二つの世界のあいだで
それからの日々、彼はまるで“ふたつの世界”を行き来しているような感覚に包まれていた。
ひとつは、これまで通りの銀行の世界。
スーツに身を包み、整った資料を手に、冷静に数字を分析し、論理的に判断を下す。
そこには一分の迷いも許されない、完成された「プロ」としての自分がいた。
もうひとつは、あの本を読んでから生まれた、“もう一つの世界”。
感情の機微や、自然の声、失われゆく風景に目を向け、
「経済とは何か」「豊かさとは何か」「お金とは何か」と、自分自身の内側に問いを重ねていく時間だった。
そして彼は、気づき始めていた。
これまで自分が“正しい”と信じていたことが、
誰かにとっては“痛み”や“犠牲”の上に成り立っていたということに。
**
ある日、上司との定例ミーティングでのこと。
「A建設との案件、早めに融資承認に進めるように。地域活性のモデルケースになるぞ」
真面目な顔で語る部長に、彼は思わず口を開きかけた。
けれど、声にはならなかった。
胸の奥に、何かが詰まっていた。
(あの土地の、森のことを話したところで、何になる?
どうせ“感情的すぎる”と一蹴されるのがオチだ……)
自分の中に芽生え始めた“もうひとつの視点”を、この場所では語れない。
語ってはいけない。
そんな無言の圧力が、この職場の空気にはあった。
会議室の窓の外に、ビルの谷間に咲く、ひとつの小さな木が見えた。
その小さな緑だけが、彼の心に寄り添っているようだった。
**
数日後、彼は週末を使って、再び母の故郷の町を訪れた。
すでに重機が入り、木々の多くは伐採されていた。
昔の美しい風景が、見る影もなく変わり始めていた。
それでも、丘の上に一本だけ残った大きな木の下に立ち、彼は静かに目を閉じた。
蝉の声、川のせせらぎ、祖父母の笑顔。
かすかな記憶が、胸の奥にやわらかく広がっていく。
(この場所を壊すことに、自分は関わっている。そして、その延長線に、地球環境を壊すことにつながっている。)
その事実が、心の深くで、重くのしかかっていた。
**
帰りの新幹線の中、窓に映る自分の姿を見ながら、彼は静かに息を吐いた。
「どちらかを捨てろ」と誰かに言われたわけではない。
だが、もう“両方を保つ”ことは、自分の本心が許さない気がしていた。
揺れる心。
見ないふりをしてきた現実。
変わりたいという想いと、それを封じ込めてきた社会の構造。
そのすべてが、今や、彼の中で音を立てて崩れかけていた。
彼の内側で、はっきりとした言葉がひとつ、浮かび上がってきた。
「このままでは、自分自身が壊れてしまう」
それはまだ確かな“答え”ではなかった。
けれど、もう“何かを決断する時”が来ていることだけは、はっきりと分かっていた。
静かに、人生の扉が、別の方向へと開き始めていた。
第5章 心の声に従うとき
すでに工事は進んでいた。
重機が唸りを上げ、森の木々は切り倒され、土が削られ、コンクリートの基礎が打たれ始めていた。
だが、最終段階に必要な大口融資――それが下りなければ、開発は途中で止まる。
上司たちの承認印はすでに揃っている。
本部の稟議も通過し、形式的にはあとは“担当者“である彼の“確認印”を押すだけだった。
銀行という組織において、決裁印は単なる事務手続きではない。
それは、「自分がその責任を引き受けます」という署名にも等しい行為だった。
彼はゆっくりと印鑑を手に取り、しばらく眺めた。
押せば、すべてが動き出す。
森が、記憶が、風景が、確実に失われていく。
彼の呼吸が、浅くなった。
次の瞬間、印鑑を戻した。
力なく、だが確かな動きだった。
心が、押すことを拒絶していた。
その足で、彼は意を決して、部長のもとを訪れた。
「……会社を、辞めさせていただきたいと思っています」
一瞬、空気が止まった。
「……は?」
部長の顔がこわばる。
「君、何を言ってるんだ。突然すぎるだろう。何かトラブルでもあったのか?」
「いえ。ただ……どうしても、自分の心が、もうここにいられないと言ってるんです」
しばらくの沈黙のあと、部長は深いため息をついた。
「まったく……君みたいな優秀なやつが、なんでこんな馬鹿なことを……」
その夜、実家に電話をかけると、案の定、母は心配の声を上げ、父は激怒した。
「なぜ相談しなかった。一言でも言ってくれれば止めたのに、この愚か者!」
彼は何も言い返さなかった。ただ、深く頭を下げて、電話を切った。
その瞬間、自分が“社会”からも、“家族”からも切り離されたような孤独を感じた。
何も持たない、何も守っていない、空っぽの自分だけが、静かな夜に浮かんでいた。
**
しばらくの間、彼は都会を離れて、心の赴くまま旅をした。
ある日、山奥の小さな駅でふと降りて、地図にもない森の小道を歩いていくと、木漏れ日の先に、ひっそりとした集落が現れた。
家は、決して大きくはなかった。
けれど、自然と寄り添うようにたたずみ、見たことのない不思議なテクノロジーがさりげなく使われていた。
お米や野菜、果物を育て、収穫を分け合い、
必要なものを必要なだけ、互いに融通し合って生きている人々。
彼らの着ている衣服は、どれも自然の素材のようで、肌になじむ優しい色をしていた。
不思議なことに、初めて訪れたよそ者の彼に対しても、
集落の人々はごく自然に、あたたかく接してくれた。
誰も詮索せず、ただ「今ここにいる自分」をそのまま受け入れるような眼差しだった。
そして、集落の中心には、小さな神社があった。
石段の上にたたずむその社は、森の息吹と調和するように静かにたたずんでいた。
静かな風が、彼の髪をなでるように通り過ぎていった。
彼はまだ知らなかった。
この場所が、自分にとって“運命の場所”になることを。
第6章 心が豊かさに還る場所
その集落での暮らしは、彼の予想を大きく超えていた。
まず驚いたのは、住人の間でお金のやりとりが一切存在しないということだった。
誰もが自分の得意なことを持ち寄り、無償の奉仕で暮らしが成り立っている。
作物を育てる人、食べ物を作る人、衣服を縫う人、建物を修繕する人、音楽を奏でる人、子どもを見守る人――
それぞれが、自分の“役割”を自然に受け入れて生きていた。
とはいえ、すべてを自給しているわけではない。
何人かは定期的に外の街へ出て働いたり、インターネット上で仕事をしたりして、必要なお金を集落のために稼いでいる。
けれど、それすらも「義務」ではなく、「流れに委ねる」ようなものだった。
**
その日、彼は一人の少女に出会った。
年は十代半ばくらいか、
髪には草花がさりげなく編み込まれていて、
まるで森の精霊と姉妹のような雰囲気をまとっていた。
少女は、川辺で小さな花に話しかけていた。
「ありがとう。今日もきれいに咲いてくれて」
そう話す声には嘘がなかった。
「……花と話せるの?」と彼が思わず尋ねると、
少女はさらりと答えた。
「話せるというか……分かるのよ。
この世界のすべてには魂があるの。」
彼は言葉を失った。
だけど不思議と、その感覚が自分の奥にもしっくりと入ってきた。
**
少女は彼に尋ねた。
「ねえ、あなたは何が得意?」
彼はちょっと照れくさそうに笑って答えた。
「うーん……経済、かな。数字を見たり、仕組みを整えたり。
でも、ここじゃあんまり意味なさそうだけど……」
少女はうれしそうに微笑んだ。
「そんなことないわ、豊かさの意識はここでも大切なのよ。
ちょうどいいから、癒しの神社の癒しの日課の一つに、“豊かさの瞑想”っていうのがあるの。
それ、ぜひ体験してみて」
彼女に導かれて、彼は集落の中心にある小さな神社を訪れた。
そこでは毎日3回、人々が静かに座り、目を閉じてしばらくじっとしていた。
少女は教えてくれた。
「まず、自分の心を点検するのよ。
今、自分の中に“お金に関する不安や心配”が生まれていないか。
知らずに“欠乏の念”が心に入り込んでいないか。
それを丁寧に見つめ、豊かさとつながる瞑想を行うの。」
彼は興味を持って聞いた。
「豊かさとつながる瞑想って何?」
少女は嬉しそうに答えた。
「呼吸を整えながら、自分は満ちていると感じていく。
目に見えるものではなく、内側の感覚で。
立体的に、現実的に、豊かで満たされた自分を“すでに在るもの”として味わうの。」
彼は少女に尋ねた。
「でも、ここでの暮らしって、お金はいらないし、
豊かさの瞑想は必要あるの?」
少女は静かに首を縦に振った。
「必要よ。だって、都市や街ではまだ、多くの人が“お金”に苦しんでる。
恐れたり、怒ったり、罪悪感を持っていたり。その意識が貧困を現象化させるのよ。
そして、その“念”って、ここにもちゃんと届くの。
だからわたしたちは、豊かさの意識を保つために心をお掃除するの」
そして、少し声を落としてこう言った。
「それにね、年に2回“豊かさのお祭り”があるの。
そのときは、集落のみんなで祈るの。
“全人類が、不足の苦しみから癒されて、本来の豊かさにつながれますように”って」
彼はその言葉に胸を打たれた。
“経済”という言葉の奥に、ほんとうの“豊かさ”があるとしたら?
それは奪い合いや競争ではなく、分かち合いと信頼の循環なのかもしれない。
彼はこの集落で、およそ三ヶ月を過ごした。
もちろん、無料で。
心がほどけ、呼吸が深くなり、
自分の存在そのものが、ようやく本当の世界とつながり始めたような気がしていた。
**
やがて彼は、都会の自宅に戻った。
雑踏の中を歩く人々の疲れた表情、
忙しさの中に消えかけた“心の声”――
かつては気づかなかったその“叫び”が、
今の彼には、痛いほどに感じられた。
「人々に、本来の豊かさを伝える仕事をしたい」
その想いが、静かに芽吹いていた。
まだ具体的な形はなかったけれど、
その種は、確かに彼の胸の中で光っていた。
それは、かつて彼が“失ったと思っていたもの”と、
もう一度出会いなおす旅のはじまりだった。
あとがき
本作は、お金を否定する物語ではありません。
むしろ、「お金」という、もっとも身近で、
もっとも多くの人が悩み、すれ違い、
そして目をそらしてしまうテーマを通して――
あなた自身と、世界の“見え方”を見つめ直すための
“目覚め”の物語です。
知らず知らずのうちに心に刻まれていた、
お金に対する不安、罪悪感、怒り、そして恐れ。
それはやがて、
心の奥に“影の塔”のような、重たい構造を
築いていたのかもしれません。
もし、この物語を読み終えた今、
あなたの内側で何かが静かに揺れ動いているなら――
それはきっと、
あなたの中の“本当の豊かさ”が目を覚ましはじめた合図。
そして、その目覚めの続きを歩むために、
あなたのための“特別な旅“をご用意しています。
🕊 オンラインスクール特別講座
「本当の豊かさを思い出す:愛と悟りの経済意識講座」
この講座は、
“経済”という言葉の奥に眠る
命の循環と、内なる真実を思い出すための時間です。
答えを与えるものではありません。
あなた自身の内に、もうある“真実”と再会するために。
物語の続きを生きるのは、
他でもない、“あなた”です。
🌿 詳細は画像をクリックしてください。

