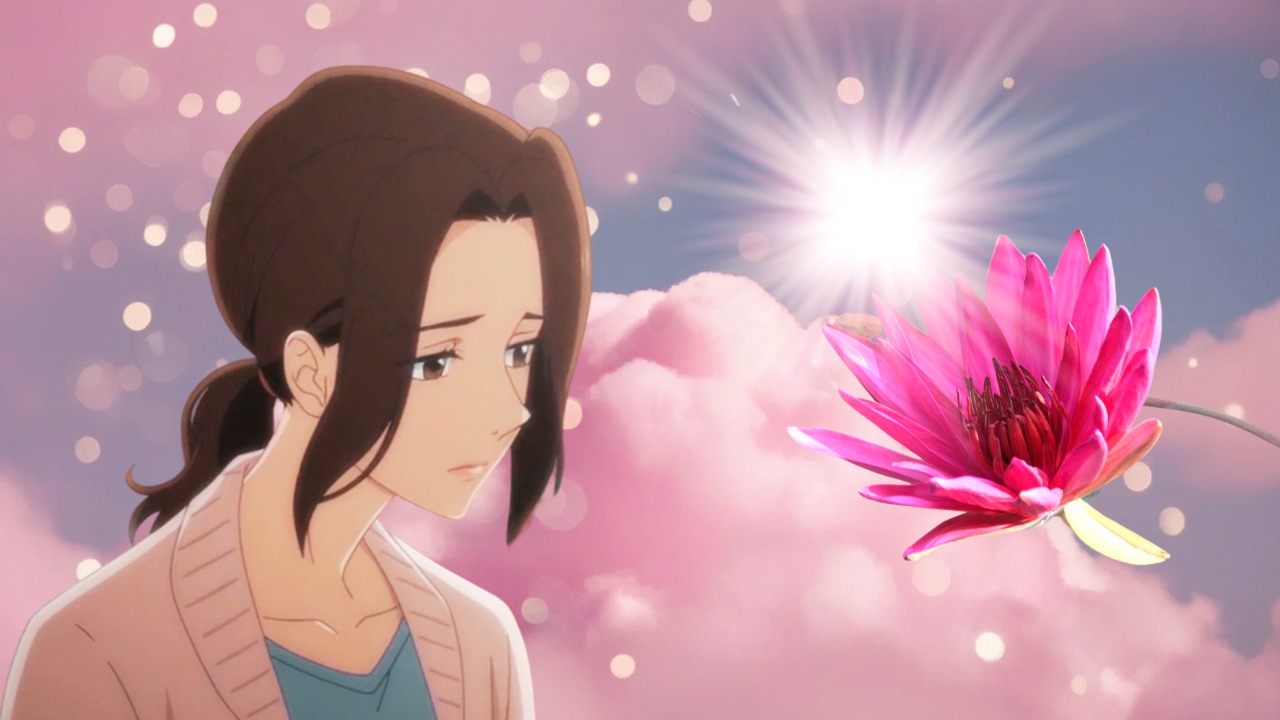


小さな咳が教えてくれたこと
「わたしが癒されることが、この子のためになる」その言葉に触れたとき、家族の未来は静かに変わり始めた。何が幸せで、何が苦しみか分からなかった女性が、本当の幸せに目覚める物語。
第一章 咳と、見えない檻
「…ゲホッ、ゲホッ…!」
また始まった。
子どもの咳で目が覚めたのは、これで何度目だっただろう。
時計の針は午前3時を指している。窓の外は静かで、誰もいない世界のよう。
けれど、ベッドの隣では、5歳の息子が、また喘息の発作を起こしていた。
身体を起こして背中をさすりながら、いつもの吸入器を手に取る。
「もう大丈夫、落ち着いて、ゆっくり呼吸して」
そう言いながら、自分の心がまったく落ち着いていないことを知っていた。
主人公の女性は、今年33歳になる。
もう何度、こうして夜中に起きただろう。
慣れた、と言えばそうかもしれない。
でも本当は――慣れたふりをしているだけだった。
病院に何度も通った。
薬も吸入も漢方もやった。
アレルギー検査も受けた。
医者には「ストレスも関係しているかもしれませんね」と言われたけれど、
その「ストレス」が、何なのか、よく分からなかった。
――わたしが、ちゃんとしていればいいんでしょう?
彼女は、自分の感情をほとんど外に出さない。
怒らないし、泣かない。
笑ってさえいれば、大丈夫。
そうやって生きてきたし、それが“普通”だと信じていた。
朝、夫が出かける。
出勤前の家は、いつも妙な緊張感に包まれる。
彼の態度は日によって違う。
何も言わずに黙って出ていく日もあれば、
些細なことで不機嫌になり、声を荒げる日もある。
「靴下が見つからないのはお前のせいだろ」
「なんでいつもこうなんだよ」
その声に、彼女は無意識に体を強ばらせる。
すぐに「ごめんなさい」と口にしていた。
悪いのは自分。
もっとちゃんとできていれば、何も起こらないはず――
いつから、そう思うようになったのだろう。
言葉にできないけれど、どこかでそう信じていた。
帰宅時も、同じだった。
玄関のドアが開く音に、空気が静かに凍る。
笑顔で「おかえりなさい」と言うけれど、
その裏では、無言の緊張が家全体に走っていた。
夫は家族に興味がないわけではない。
けれど、何かがうまく噛み合わない。
話そうとすると、すれ違いになる。
わかってほしい気持ちは、お互いにあるのに。
小さな息子は、そんな大人たちの心の気配を
何も知らないふりをしながら、
実はすべて、感じ取っていた。
子どもの体は、言葉の代わりに反応する。
言葉にならない想いが、咳となって現れる。
それが“喘息”というかたちをとって、今ここにある。
でも、誰もまだ気づいていない。
母親も、ましてや自分の感情が鍵になるなんて思ってもいなかった。
「わたしが、我慢すればいいのよ」
その思いが、習慣になり、
やがて、檻になっていった。
その檻の中で、彼女は静かに息をひそめる。
息子もまた、同じ檻の中で、
小さな肺をひくひくと震わせていた。
第二章 出会いの扉
「どうして……良くならないの?」
薬も病院も、ありとあらゆる方法を試した。
けれど症状は一進一退で、夜になると苦しそうな咳が、家じゅうに響きわたる。
まるで、何かを訴えるように。
主人公の女性は、静かな夜の中、眠れぬまま子どもを抱きしめていた。
目を閉じるたびに、喉を裂くような咳が背中を震わせる。
一般的な治療に限界を感じていた彼女は、深夜、スマホの小さな画面に希望を求めていた。
そして目に留まったのが、ある小さなクリニックの紹介記事だった。
「身体の症状は、心や魂の声を映す鏡です。」
一文が、胸に刺さった。
ただのコピーライティングではない。
彼女はそう感じた。
――この人なら、何か知っているかもしれない。
翌朝、すぐに予約を入れた。
⸻
数日後。
クリニックの扉を開けると、そこには柔らかな光に包まれた空間が広がっていた。
ピンク色でシンプルに飾られた診察室には、無機質な冷たさはなかった。
花の香りがかすかに漂い、まるで誰かの家に招かれたかのような安心感がある。
そして奥にいたのは、白衣をまとった女性医師。
鋭さはなく、穏やかで柔らかな眼差しをたたえた女性だった。
「こんにちは。お待ちしていました。」
その声に、彼女は思わず胸の力が抜けるのを感じた。
症状についてひと通り話し、子供への診察が始まる。
そして、医師は、身体が“本来の自然治癒力“を引き出す食事療法などの説明を終えると、カルテを閉じ、まっすぐに彼女を見つめた。
その瞳には、医者というよりも、母のような温かさがあった。
「確かに、お子さんの咳は身体の症状です。薬も必要なときはあります。
でもね……身体に表れるのは“氷山の一角”なんです。」
主人公は、思わず眉をひそめた。
「その下には、心の緊張や感情の揺れが隠れていることが多いんですよ。」
「……心が、咳に関係あるんですか?」
医師は微笑みながら頷いた。
「緊張すると肩がこる。不安が続けば、胃が痛む。
呼吸も同じなんです。
心が安らげば深くなり、不安や恐れがあると浅くなる。
咳は、心の波立ちが呼吸に表れた結果かもしれません。」
彼女の中に、小さな“納得”が芽生えた。
思い返してみれば、夫から責められた日や、誰にも話せない不安を飲み込んだ夜に限って、
息子の咳はひどくなっていた。
だが、医師はそこで話を終えなかった。
「そして――心のさらに奥に、“魂”という存在があります。」
「魂……?」
「そう。目には見えないけれど、本当の自分を映す“源”のような存在。
魂が求めていることを無視して生きていると、
その歪みが心に、そして体にあらわれることがあるんです。」
その言葉に、彼女は息を呑んだ。
「お子さんは、お母さんの心と魂に、とても敏感に共鳴しています。
だから、お母さんが魂のレベルで安らいでいくと、その響きは自然と伝わるんです。」
「……わたしの魂が、この子に?」
「はい。だからこそ――“あなたが癒されること”は、この子を癒すことにつながります。」
医師はゆっくりとそう語った。
「無理に何かを変える必要はありません。
小さな安心、小さな喜び、魂が微かにでもほっとする瞬間を、自分に許すだけでも違います。」
彼女の胸に、静かに光が灯った。
けれど――その光の奥には、戸惑いもあった。
「わたしが癒されることが必要……?
でも、病気を持っているのは息子だし、わたしは別に病気じゃないし……。
わたしが何を癒せばいいのかなんて、全然わからない。」
孤独、緊張、不安。
それは“苦しみ”という名前で呼ばれたことがなかった。
当たり前すぎて、あえて意識したことすらなかった。
――「わたしが苦しんでいる……? 本当に?」
その問いは、まだ答えを持たないまま、
けれど確かに、彼女の内側に扉を開いた。
次の扉へと、続いていく静かな気配だった。
第三章 心の奥の声
主人公の女性は何回か診療に通い、少しずつ、身体をケアしながら心と魂の声に耳を傾けるという、斬新的な医療の形を理解していった。
そしてある日、再びクリニックを訪れた主人公に、白衣の女性医師がこう語りかける。
「心の準備ができたみたいなので、今日はちょっと深い癒しを行いましょう。目を閉じて、少し深呼吸してください。」
その声は、いつも変わらず静かで温かかったが、どこか“奥行き”を感じさせた。
――これは、何かが始まる予感。
そう思ったとき、彼女の胸が、わずかに緊張で固くなった。
「今日の診察では、お子さんの話ではなく、“あなた自身”の内面に少し意識を向けていきますね。」
彼女は思わず、姿勢を正した。
「……わたしの?」
「はい。あなたの抑圧している感情、普段気に留めない、無視してしまっている思い。
それらに、そっと光を当てていきます。」
「……まだよく分からない、そんなの、本当にあるんですか……?」
「大丈夫です。ただ目を閉じて、わたしの声に意識を向けていてください。」
⸻
深呼吸。
目を閉じる。
音のない空間。
彼女の心は、最初は何も感じない、よく分からない状態。
女性医師は優しく、彼女が心の奥の苦しみが見えるように時々メッセージを伝えていた。
そして、しばらくすると、胸の奥に微かなざわめきが現れた。
「……ちゃんとしなきゃ。」
それは、長年聞き慣れた心の声だった。
「ちゃんと母親でいなきゃ。ちゃんと笑って、ちゃんと仕事して、ちゃんと支えて……。」
“ちゃんと”という言葉の奥に、ずっと無視してきた疲れがあった。
「でも、本当は――もう限界なのに。」
胸が痛んだ。
でも、その痛みさえも、これまでは見ないようにしてきた。
*
さらに奥から、別の声が浮かび上がってくる。
「どうして私ばっかり……。」
それは、不満とも怒りともつかない、混ざりあった感情だった。
「夫はいつも他人事みたいで。
わたしがどれだけ眠れなくても、責めるだけで。
……わたしばっかりじゃない……!」
思わず、両手に力がこもる。
そしてその手が、わずかに震えていることに気づく。
「……怒ってる。わたし、ずっと怒ってたんだ……。」
気づいた瞬間、涙が一粒、頬を伝った。
泣くことを忘れていた。
泣く余裕なんてなかった。
泣いたら、壊れてしまいそうだった。
「……怖かったんだ……。」
誰にも頼れないと思っていた。
自分が崩れたら、すべてが崩れると思っていた。
皆が困るから、自分が皆を支えないといけないと思っていた。
だからこそ、感情を押し込め、笑っていた。
“いいお母さん”として。
“ちゃんとした大人”として。
でも、本当の自分は――ずっと叫んでいたのかもしれない。
「助けてって……。」
静かな沈黙。
けれどその沈黙の中に、今までにない“ゆるみ”があった。
力を入れていた肩の奥が、ゆっくりと溶けていくような、
どこか遠くから、温かい風が吹き抜けていくような――
⸻
「……なんですか、これは……?」
彼女は目を閉じたまま、ぽつりと声をこぼした。
「なんだか……不思議と、楽になってきました……。」
まるで、大きな手のひらで包み込まれているような安心感が、内側から溢れていた。
女性医師は、微笑みながら答える。
「これは、宇宙に充満している“癒しのエネルギー”なのです。」
「……宇宙に……?」
「はい。
目には見えないけれど、愛のように、あたたかく流れている。
意識から意識へ、波のように伝わるエネルギーです。」
「……意識から……意識へ……。」
「あなたが、自分の感情を否定せず、ただ“認めた”からこそ、
このエネルギーは、今、あなたの中に流れ込んできたのです。」
彼女の心に、静かな光が灯っていた。
それは“答え”ではなかったけれど、
“向き合う覚悟”のようなものだった。
その瞬間、ふと――
彼女の内側で、
今まで気づかなかった「苦しみ」が、形を持って浮かび上がってきた。
けれど、それはもう、恐れるものではなく、希望が混ざっていた。
第四章 本当のわたしが顔を出すとき
女性が診察を受け始めてから数ヶ月が経っていた。
胸の奥にはまだ、あの“淡い痛み”が残っている。
今まで気づかぬふりをしてきた感情の名残。
涙と一緒に、閉じ込められていた何かが少しずつ溶け出しているのを感じていた。
そして、ある診察の日のこと、
女性医師との会話のやり取りで、ふと昔のことを思い出した。
「なんで、またそんな夢みたいなこと言ってるんだ。お前は現実を見ろ。」
それは、父の声。
昔から彼は、いつも“現実は厳しいぞ、なんでそんな甘いこと言ってるんだ”と怒鳴っていた。
美しいものや心の話には目もくれず、
「そんなもので飯が食えるか」「時間のムダだ」と切り捨てた。
父の言う“現実”は、いつも数字と肩書きの世界だった。
成功とは何か。
価値とは何か。
答えはすべて“外側”にあると信じて疑わなかった。
彼の目に、魂なんて映っていなかった。
⸻
一方で、母は違った。
優しかった。
静かに見守ってくれていた。
でも――
いつも、どこか“怯えて”いた。
「あなたはやりたい事をやりなさい」
そう言いながら、
どこか不安そうな眼差しで、わたしを見つめていた。
その眼差しには、口に出されないメッセージがあった。
「でも、失敗しないでね」
「でも、変な道に行かないでね」
「でも、傷つかないでね」
そう、“心配”という名の見えない手綱が、
いつもわたしの背中にそっと巻き付いていた。
⸻
「わたしは……誰に、何を期待されてきたんだろう」
そんな問いが浮かぶ。
父には“現実的に生きろ”と。
母には“いい子でいてね”と。
表面的には自由を与えられているようで、
深いところでは、心の奥を閉じることを求められていたのかもしれない。
気づいたとき、ふと、手が震えていた。
「だから……わたし、ずっと、感受性を“隠して”生きてきたんだ……」
「感じすぎると、怒られるから」
「泣くと、弱いと思われるから」
「夢を語ると、馬鹿にされるから」
子どもの頃から、
父の顔色をうかがい、
母を悲しませないように、
“本当の自分”を奥の奥に閉じ込めてきた。
その結果――
笑っているのに、いつも苦しい。
自由なはずなのに、なぜか罪悪感がある。
愛されているのに、なぜか孤独。
「……この苦しさの正体、これだったんだ……」
静かに涙があふれていた。
白衣の女性医師が言った。
「お父様は守ろうとすることに目が眩んで厳しくなり、愛情の表現を忘れていたのでしょう。
お母様も義務感の中で自分を失い、どうして良いか分からなくなっていたのかもしれませんね。そして、抑圧された感情の奥には、“ほんとうの願い”が眠っているんです。それこそが魂の望みなんです。」
ほんとうの願い?魂の望み?
それは、きっと――
「ただ、“わたし”でいたい」
「誰かの期待ではなく、“わたし”として生きたい」
そんな、あまりにも素朴で、でも切実な願い。
それを口に出すことすら、これまで許されなかった。
「わたしには、そんな価値も能力もない」と思っていたから。
でも今、その“思い込み”が静かにほどけていくような気がした。
閉じられていた感受性。
押し込められていた優しさ。
蓋をされた創造性。
それらが少しずつ、光の下に顔を出し始めていた。
「もう、大丈夫だよ」
そう、心のどこかで自分自身にささやいていた。
ほんとうの自分に出会う旅が、今、ようやく始まろうとしている。
「……やっぱり、今日も来てよかったです。」
暖かな雰囲気が香る診療所で、女性は小さくつぶやいた。
そして、天井をぼんやり見つめながら、ぽつりと言った。
「身体も、心も、“安全だ”と感じる場所があると、初めて本音が出てくるものなんですね。
わたし……
ずっと、“わたしじゃない誰か”を生きてたみたいです。これからは、わたしの本当の思いを生きたいです。」
女性医師は、微笑んだ。
第五章 癒しは静かに、でも確かに
あれから、いくつもの夜を越えてきた。
驚くことに、夜の発作の数は目に見えて減っていた。
少し前までは、眠りにつくのが怖かった。
「また苦しくなるんじゃないか」「子どもがまた発作を起こすんじゃないか」
そんな不安が、いつも寝室の空気を張りつめさせていた。
でも今は、違う。
わたしも子どもも、ようやく“安心して眠れる夜”を迎えられるようになっていた。
夫にも、変化があった。
以前は、無言。
命令口調、短く冷たい返事、八つ当たり。
そんな“感情の壁”が夫婦の間にいつも立ちはだかっていた。
だけど最近――
「今日は大丈夫だった?」
「いつもありがとうな」
「無理、するなよ」
少しずつ、けれど確かに、“優しい言葉”が増えてきている。
何より、あの怒りの裏にあった不安や孤独が、わたしの中で見えてきたから、
もう必要以上に傷つくことが減ったのかもしれない。
わたしの内側の変化が、目の前の現実を変え始めている。
そんな気がしていた。
⸻
久しぶりに両親から連絡があり、不思議な出来事を話していた。
母はなんと、長年通っていたコーラスで、ついに「自分が企画・運営するコンサート」を立ち上げたという。
「本当にやるとは思わなかったわよ、自分でも」と、笑っていたけれど、
その声はどこか張りがあって、明るかった。
あんなに「やりたいけど…」とブレーキをかけ続けていた母が、
今、何かを超えて動き出している。
そして、父。
科学しか信じず、芸術や表現の話には耳も貸さなかった人が――
なんと、母と一緒にコーラスで歌っているというのだ。
「意外と楽しい」と、照れくさそうに父が話す。
あれだけ頑固だった父が、少しずつ丸くなり、
人間の中の“美しいもの”に目を向け始めている。
長年痛みを訴えていた母の腰も、最近は調子が良いらしい。
⸻
次の診療日、わたしはいつになく嬉しい気持ちで診療所に向かった。
変化は、巷で言う“大袈裟な奇跡”のような派手さではない。
でも、確かに奇跡は起きている。
身体の奥、心の奥、家族の空気の中に。
その日の診察の終わり、女性医師が静かに話し始めた。
「喘息の状態、かなり落ち着いてきましたね。嬉しいです。」
わたしは深くうなずいた。
医師は、カルテを閉じながら、静かに続けた。
「でも、病気の“完全なる治癒”ということに関しては……本人の魂の課題も関わっているので、長い目で見ていきましょう。
少し不思議に思われるかもしれませんが、わたしは、医者として、こう思っています。」
彼女の目は真剣だった。
「実は、病気を“治す”ことが医学の本当の目的ではないんです。」
わたしは驚いて、医師を見た。
「人が幸せを感じられるよう、心と体を整えるサポートをする。
それが、医学の本質だと、わたしは思っています。
わたしのこの思いは、まだ医療の世界ではかなり少数派ですね。」
女性医師は、深い慈悲の眼差しを持って語り始めた。
「多くの医者が、心や魂に目を向けず、対症療法だけで、症状だけに対して薬や手術などで対応しています。
もちろん、対症療法は、緊急の場合には必要ですので、存在意義は大いにあるのです。
ただし、それだけに偏ってしまうと、根本的に病気は治らないのです。
大抵の場合は、症状を見えないようにするだけで、心や魂に病気は残っているのです。
わたしも医学を学び始めた頃は対症療法だけを行なっていました。初めは一般的な規定に従い診療し、薬を処方して何も考えずに仕事をしていました。
ある時から、病気をどうにか“治そう”として、多く悩み、心をすり減らすようになりました。自分が無力だと感じてしまうこともありました。
でも、患者さんの心に寄り添っているうちに、現代医学の限界が見えてしまったのです。
それから、様々な研究をはじめました。まず、より自然に近い統合的な療法。そして、心のあり方がどのように身体に反映されているか。さらに、魂の存在。
その過程で、多くの同僚から奇異の目で見られたり、批判されたりすることもありました。」
女性医師は少し微笑みながら続けた。
「そして経験を通して学んだことは、身体を正しくケアし、心と魂にアプローチすることで、多くの病気は根本的に治すことが可能だと言うこと。でも実は、全ての病気が治るわけではないのです。年をとればどこかに体の不調は起こってきますし、魂の成長に必要で起きている病気も存在する。今世では対応できない病気もある。
わたしの中での結論として、
身体は完璧にはなれない、そして、
身体は元気でも、心が苦しければ人は幸せではないし、
反対に、体の不調や病気とうまく共存しながら、幸せに生きるという選択肢もあるのだということ。」
とても深い内容に、しばらく沈黙が流れた。
わたしは、胸の奥が静かに震えているのを感じた。
「……先生。ありがとうございます。」
それは、ただの感謝ではない。
心の底から湧き上がる、命への感謝だった。
苦しみと向き合う中で、
わたしはようやく“本当の自分”に会いに行く決意ができた。
ただ子供の病気を治すために通っていた場所が、
いつの間にか、自分の魂に出会うための道しるべになっていた。
「わたし、癒しを、続けていきたいです。」
女性医師が穏やかに微笑む。
「それは、病気を治すためというよりも……
日々、愛と幸せを育んでいくということですね?」
わたしは静かにうなずいた。
「はい。
そして、もっと……
“わたしの魂が本当に望んでいること”を、見つけていきたいと思っています。」
女性医師は優しく答えた。
「それが本当の愛であり、幸せの道であり、癒しの道なんです。」
癒しは、終わりではない。
癒しは、新しい人生の始まりなのだと――
わたしは、ようやく知った。
― 完 ―
もしこの物語が心に響いたなら、
気づきを必要としている誰かに、そっと届けていただけたら嬉しいです。
