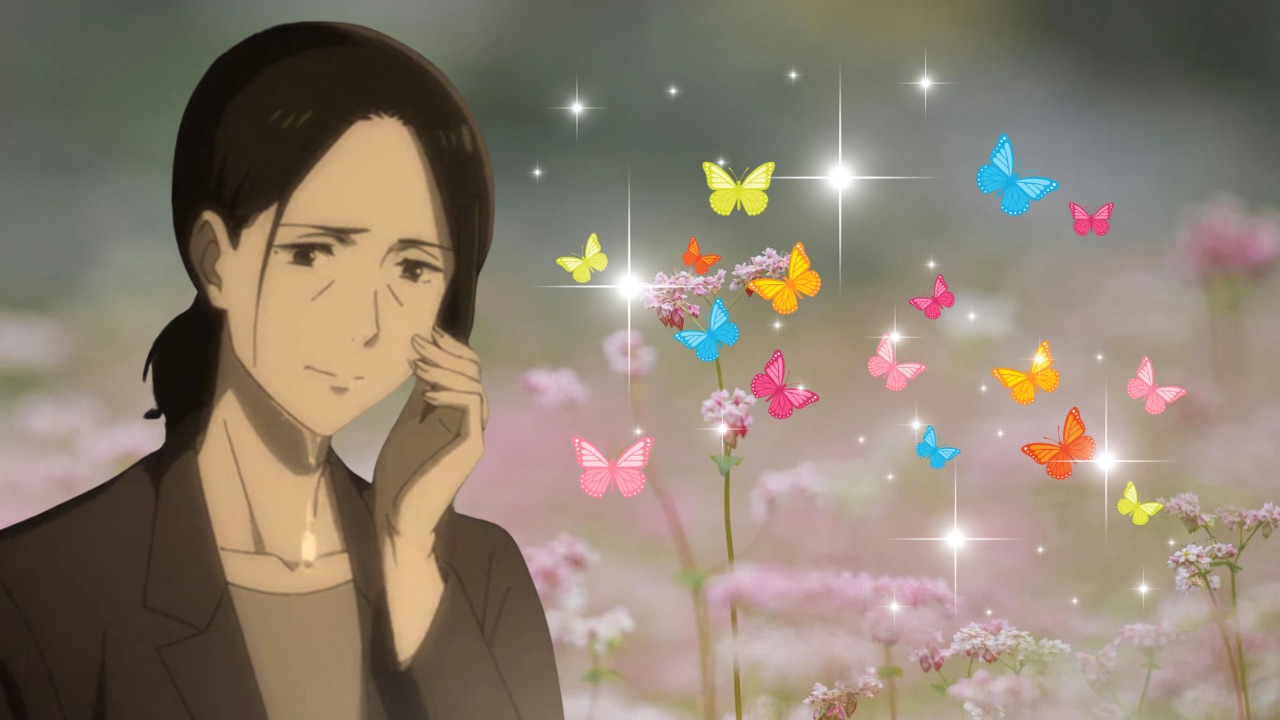


正しさの仮面の裏側にあった間違い
「なんでわたしばっかり…」心がそう呟いたとき、わたしは我慢の限界を超えていた。真面目に生きてきた“正しい人”が、自分の本心を取り戻す。インナーチャイルドの癒しの物語。
プロローグ
「先生って、正しいことしか言わないけど……
なんか、ずっとつらそうに見えるときがあります」
ある日、教室で、生徒にそう言われた。
冗談だと思って笑い飛ばそうとしたけれど、
その言葉は、まっすぐ胸の奥に突き刺さった。
わたしは間違ってなんかいない。
誰かがしっかり教えなきゃ、
この子たちは将来、困るんだから。
ずっとそう信じて、
厳しく、真面目に、まっすぐにやってきた。
でも──なぜだろう。
「正しいはずの言葉」を口にするたび、
生徒たちの目が、少しずつ冷めていく気がした。
気づかぬうちに、
わたしはきっと、自分自身を裁く“先生”になっていたのかもしれない。
ずっと頑張ってきた。
……でも、心のどこかで、ずっと泣いていた。
「なんでわたしばっかり」
「どうして、誰もわかってくれないの」
その声は、いつからか封じ込めていた、幼いわたしの声だった。
その小さな声が聞こえたとき、
わたしは初めて、“正しさの仮面”を脱ぐ──心の旅に出ることになった。
第1章 正しさの檻の中で
「廊下は走らないって言ったよね」
「提出物、期限を守りなさい」
「言い訳なんて、大人になったら通用しないよ」
黒板の前に立つわたしは、今日も“正しさ”の言葉を繰り返していた。
クラスは静まり返り、生徒たちは視線をそらして黙っている。
けれど、わたしの中では何かがざらついていた。
──ほんとにもう、何でこんなことも守れないの?
心のどこかで、無言の怒りがいつもささやいていた。
放課後、ふと見上げた教室の時計。
一分も早く終わらせたいと願っていたのは、生徒ではなく、わたしだった。
その夜、実家から電話があった。
母の声は少し弾んでいた。
「今度、お姉ちゃんと一緒にヒーリングの講座に参加するのよ」
「すごくいいの。心がね、軽くなるの」
「あなたもどう? 真面目なあなただからこそ、必要だと思うの」
また、姉の話だ。
一つ年上の姉は昔から何でもできた。
成績も良く、運動もできて、性格も明るい。
わたしはずっと、姉の「ついで」の存在だった。
「わたしはいいから。そんなの、わたしには合わない」
電話を切ったあと、胸に広がるのは怒りと悲しみだった。
「また、わたしだけがダメなんだ」と心の奥がざわつく。
何も言っていないのに、責められた気がした。
寝つけない夜。
ふと、小さな頃の記憶が浮かんだ。
体育館のステージ上で、姉が表彰されていた。
わたしも笑って拍手をしていたけれど、
心の奥では、悔しさと孤独が燃えていた。
「どうせわたしは……ダメな子だから」
その呟きが、今も心のどこかに残っている。
だからわたしは、もう間違えちゃいけない。
完璧でなければ、誰にも愛されない。
そう信じて、大人になった。
翌朝、職員室で教材の整理をしていたとき、隣の先生がふと声をかけてきた。
「ねえ、昨日のあの叱り方、ちょっと強すぎたんじゃない?
最近の子たち、ああいう言い方には敏感だからさ」
わたしはすぐに反論した。
「でも、ふざけたことをしていたんですよ?
見逃してたら、どんどんエスカレートします。
“今”ちゃんと教えなきゃ、将来困るのはあの子です」
「うん、まあ、そうだけど……」と、その先生は少し言い淀んだ。
その様子を見て、わたしは心の中で思った。
(…甘すぎる。今どきの先生って、子どもに嫌われたくないだけじゃないの?)
自分は“ちゃんと”やっている。
間違ってるのは、甘い態度で見過ごす他の先生たち。
そう、みんな間違ってる。
正しいのは、わたし一人だけ――。
第2章 崩れはじめた日々
教室に入ると、一瞬だけ空気が揺れるのを感じた。
(また、わたしが来たから静かになった…?)
その静けさは、尊敬ではなかった。
そこにあったのは、緊張と、遠ざかる気配だった。
「授業始めます。席に着いて」
そう言った瞬間、前列に座っていた女子生徒が、
教科書を机にバンッと叩きつけるように置いた。
思わず、教室中の視線が彼女に集まる。
「……何、その態度」
わたしは、声をひそめて言った。
彼女は無言のまま、わざとらしく教科書をめくった。
(…反抗?わたしをなめてる?)
なぜだか、その態度がどうしても許せなかった。
「あなた、何か言いたいことがあるなら言いなさい」
その瞬間、彼女が顔を上げ、こう言った。
「先生って、正しいことばっか言うけど、
みんなが先生をどう思っているか、全然わかってないよね」
時間が止まった。
教室が静まり返る。
わたしは、その言葉に、心臓を殴られたような感覚を覚えた。
「……何それ?教師に向かって、何様のつもり?」
怒りが、理性を上書きしていく。
「あなたみたいな子がいるから、クラスが乱れるの!
反抗してる暇があるなら、少しは努力したらどうなの?」
怒鳴った瞬間、生徒たちの顔から、すっと血の気が引いた。
女子生徒は、わたしを睨みつけながら立ち上がった。
「何様? 自分の言ってることが全部正しいと思ってるの?」
わたしの中で何かが切れた。
「ちゃんと指導してるだけでしょ? ルールを守らせるのが教師の仕事です!」
女子生徒は冷たく答えた。
「ルール、ルールって、そうやって、人を潰して何が楽しいの?
あんたに人の気持ちなんてわかんないくせに!」
その瞬間、カッとなった。
頭より先に、身体が動いていた。
「いいかげんにしなさい!」
パァン!
わたしは、女子生徒の頬を叩いた。
次の瞬間――
バシン!
彼女の手が、反射的にわたしの頬を打ち返した。
教室の空気が、一瞬止まった。
ふたりとも、目を見開いて立ち尽くしていた。
(……何をやってしまったの?)
その問いが、心の中に浮かぶより早く、
「最低……」と彼女は呟き、
振り返りもせず、ドアを乱暴に開けて出ていった。
ドンッ!
激しい音が、乾いた心に突き刺さった。
教室は、しん……と静まり返っていた。
*
後日、教頭に呼ばれた。
「今回の件、保護者から強い抗議がありました」
冷静な口調だった。
でも、その目はわたしの“信じてきたもの”を、
すべて否定するような色をしていた。
「あなたは、よく頑張ってきたと思います。
でも……少し、休んでみませんか」
(……休めって?)
それは“降ろされた”という宣告にしか聞こえなかった。
「事実確認のあいだ、自宅で待機してください」
わたしはうなずくこともできず、ただ席を立った。
帰り道、空がやけに広くて冷たかった。
今までいつも、夕焼けがにじむこの道を「達成感」と共に歩いていた。
でも今日は、まるで罪を背負っているようだった。
家に着いても、ジャケットを脱ぐことさえ忘れたまま、床に崩れ落ちた。
心のどこかが、音を立てて砕けていく。
(どうして……わたしだけが、責められるの?)
怒りとも悔しさともつかない感情が、胸をぐちゃぐちゃにかき回していた。
そして、ぽつりと、口からこぼれた。
「なんで……なんで、わたしばっかり……」
誰もいない部屋に響いたその声は、
まるで幼いわたしが泣いているように聞こえた。
第3章 心を開きはじめた母
その夜、母から長いメッセージが届いた。
学校で何があったかは、何も知らないはずなのに、
胸の奥を見透かすような言葉が、ぽつり、ぽつりと綴られていた。
「ねえ、あなたにどうしても伝えたかったことがあるの。
わたしの母――あなたのおばあちゃんは、
何でも“ちゃんとしてること”が大事な人だったの。
人前ではいつも背筋を伸ばして笑って、
『恥ずかしいことしないように』って、よく言ってた。
でもね、わたしはずっと…
ほんとは怖かったの。間違えることが。
誰かにガッカリされることが。
だから、気づいたらいつも、
“ちゃんとしてるフリ”ばかりしてた。
本当の気持ちは、誰にも見せなかった。
自分でも、だんだん分からなくなっていったの。」
読み進めるうちに、胸がじんわりと締めつけられていく。
「あなたには、
そんな思いさせたくなかったのにね。
結局、わたしも同じことをしてた。
『ちゃんとしてなさい』
『人に迷惑をかけちゃだめ』
って、ずっと言ってたね。
あなたの“がんばる顔”を、
わたしは“安心のしるし”みたいに思ってた。
でも、ほんとはあのときから気づいてたの。
あなたのなかに、いつも泣いてる声があること。」
そして、最後にこう書かれていた。
「…あなたが今どんな気持ちでいるか、
わたしには全部は分からない。
でももし、今つらいなら、もう無理しなくていいよ。
泣いてもいいし、怒ってもいい。
“正しくあること”より、大切なものがあるって、
今ならわたしにも、少しわかるから。
大丈夫。
あなたがいてくれるだけで、
わたしは幸せなのよ。」
スマートフォンの画面を見つめたまま、
わたしは、何も返せなかった。
涙は出ない。
声も出ない。
けれど、
心のどこかで、
ずっと凍りついていた場所が――
ほんの少しだけ、音もなく、
揺れた気がした。
第4章 閉じかけた扉の向こうに
あの夜、母からのメッセージを読んでからも、わたしは何も返信できずにいた。
言葉を出すには、まだ心が追いついていかない、
どう返せばいいのか、わからなかった。
泣くことも、怒ることもできず、ただぼんやりとスマホを見つめる日々。
(…だから何? 今さらそんなこと言われても)
そんな声が、心の奥で小さく呟いていた。
それでも、あの言葉たちは不思議と残っていた。
「泣いてもいいよ」「怒ってもいい」――
ずっと禁じてきた感情たちに、「出てもいい」と言われたことに、
遠い違和感を感じていた。
それから数日後。
特に理由もなく、ふと「ヒーリング講座」という言葉が頭をよぎった。
(たしか、父母も姉も参加してたっけ……)
「ちょっと、そっちの世界の人たちだよね」と、
これまではどこか他人事のように思っていたその講座。
でもその日だけは、なぜか、スマートフォンを手に取っていた。
「癒しのオンライン神社」
検索して出てきたページのトップに、こう書かれていた。
「この世界には、静かに癒されていく場所がある。
― それは、あなた自身の内側に ―」
(……内側に?)
正直、よくわからなかった。
でも、わからないままに読み進めていた。
画面をスクロールすると、
「責めてばかりいた自分を、やさしく見つめ直せました」
「怒りの原因が分かり、人を受け入れられるようになりました」
「生まれてはじめて本当の愛を感じ、涙が止まりませんでした」
そんな感想がいくつも並んでいた。
(こんな言葉、今までのわたしなら絶対に鼻で笑ってたのに……)
気がつくと、日程のページを開いていた。
次回のオンライン開催は、数日後。
テーマはインナーチャイルド。
“幼い頃の心の傷が、今も大人のわたしを苦しめている”らしい。
ためらいながら、姉にLINEを送った。
「今度のヒーリング講座……もしよかったら、一緒にオンラインで参加できる?」
しばらくして、返事がきた。
「うれしい。もちろん一緒に。つないでおくね」
画面を見つめながら、
ほんの少しだけ、胸の奥にぬるい風が通った気がした。
*
ヒーリング講座の当日、オンラインで画面を開く。
ヒーラーのやわらかな声が流れてきた。
「わたしたちは、子ども時代にたくさんの“感じたくなかった気持ち”を胸にしまい込んでいます。
でも、それはなくなったわけじゃない。
今も、心の奥でずっと泣いている“自分”がいるのです」
その言葉に、喉の奥がピリついた。
(なにそれ…)
(わたしのことなんか、何も知らないくせに)
気づけば、口に出していた。
「そんなの、ただの思い込みじゃないですか。
勝手に決めつけないでください」
画面越しに視線が集まる。
わたしはヒーリングの主催者を睨みつけるように見つめた。
(…バカみたい。こんなところ、来るんじゃなかった)
少しの沈黙の後、姉がやさしく話しはじめた。
「わたしね、ずっとあなたのことが羨ましかった」
(え?)
思わず、画面越しに姉の顔を見た。
「あなた、子どもの頃、しょっちゅう病気してたでしょ?
だから父母はいつもあなたにつきっきりで…
わたしは、ひとりで我慢することが多かった。
寂しかったの。でもね、あなたが悪いわけじゃないって、やっと思えたの」
その言葉が、静かに胸に落ちた。
(……わたしが? 姉から羨ましがられてた?)
(わたしが“特別に愛されていた”なんて…思ってもいなかった)
その瞬間、自分の中で何かが崩れた。
わたしは「愛されなかった」とずっと思い込んできた。
でも、姉もまた、ずっと苦しんでいた――
わたしを責めることもなく、ただ胸の内を語ってくれた。
もう、言い返す気力なんてなかった。
そしてヒーリングが始まった。
わたしはただ静かに横になり、
気づけば、頬が濡れていた。
涙は、何かを責めるようなものではなかった。
それは、自分の奥深くで、
ずっと泣き続けていた“小さなわたし”の涙だった。
今になって、ようやく聞こえた。
「寂しかったよ」「どうして気づいてくれなかったの」
…そんな、小さな声が。
わたしはそっと、心の中のその子に言った。
「ごめんね。ずっと気づかなくて」
すると、不思議なことに、
胸の奥が、ほんの少しだけあたたかくなった。
第5章 仮面を脱ぐ勇気
あの初めてのワークのあと、
わたしは、何かに導かれるように、毎回のヒーリングに参加するようになった。
最初は内容がよく分からなかった。
でも、次第にその静けさや温かさが、わたしの心に沁みていくのを感じた。
言葉ではうまく説明できないけれど、
終わったあと、胸の奥がすこし軽くなる。
そんな体験を、何度もくり返した。
やがて、個人セッションも受けてみた。
画面越しに語られる言葉が、まるでわたしだけに向けられたもののように響いた。
――そして2ヶ月後。
復職の一日前。
再び、インナーチャイルドの癒しのワークが巡ってきた。
いつものように、オンラインの画面越しに流れる、
静かなヒーリング音楽から始まったそのワーク。
そして、言葉が、そっと届いた。
「あなたの中に、傷ついたままの小さな存在がいるのを、感じてみてください」
「その子の目を見て、こう伝えてあげてください――
『あなたはダメな子じゃないよ。間違えても、ここにいていい』」
目を閉じたまま、その言葉を心の中で繰り返す。
「……わたしは、ダメな子じゃない。
間違えても、ここにいていい――」
頬をつたう涙に気づくまで、時間はかからなかった。
見えた。
あの頃の自分。
何も分からず、ただ“正しくあろう”と頑張っていた、小さな女の子。
自分の本音より、他人の期待を優先していた、あの子。
「ごめんね……
ずっと無視してきて、ごめんね」
心の中で、小さな自分を抱きしめるように、そう伝えた。
その瞬間、胸の奥にあった何かが、すうっとほどけていくのを感じた。
プライドという名の鎧。
自分を正当化し、すべてを人のせいにする性格。
それは、傷つかないために身につけたものだった。
でも今なら、分かる。
本当に間違っていたのは、
「間違えてはいけない」と信じていた、その信念のほうだった。
完璧でいようとしていた。
そうすれば、きっと認められる。
そうすれば、愛される。
そう思って、自分にも、他人にも、ずっと厳しくしてきた。
誰かに“間違い”を指摘された時、
正しそうな言葉で相手を攻撃する。
相手が反論する余地を与えないように。
でも――
「正しさを振りかざすことが、
誰かを苦しめていた。
そして、それ以上に、わたし自身を苦しめていた」
その気づきは、やさしい痛みだった。
それでも、今なら受け止められる。
正しさの仮面が、ひとつひとつ、音もなく剥がれていく。
わたしの中に、はじめて「慈しみ」という、やわらかな愛の感覚が芽生えていた。
第6章 新しい自分としての喜び
復職の日。
朝、学校へ向かう足取りは、かつてとはどこか違っていた。
不安がなかったわけではない。けれど、あの頃のような“戦い”の気配は、もうわたしの中にはなかった。
教室に入った瞬間――
生徒たちの視線が一斉に集まる。
一瞬、緊張が走る。でも、わたしは深呼吸をして、やさしく微笑んだ。
「おはよう」
その声に、ざわめいていた空気がふっと和らいだ。
授業が始まる。
以前なら、すぐに注意していたような場面でも、わたしはまず立ち止まった。
生徒の目を見て、ゆっくりと、話を聴いた。
それは、小さな選択の連続だった。
でも、その積み重ねが、空気を変えていった。
ある日、一人の生徒が言った。
「先生……最近、なんか優しくなった気がします。
前よりも、こっちのこと、わかってくれる感じ。」
その言葉に、思わず笑みがこぼれた。
心からの、やわらかい笑みだった。
そのとき、以前トラブルになった女子生徒が、ためらいがちに口を開いた。
「先生……あのときは本当にすみませんでした。
嫌なことがあって、うまく言えなくて……先生に八つ当たりしてしまいました。」
目を伏せたその声には、幼さと真剣さが入り混じっていた。
わたしは静かに頷き、そっと言葉を返した。
「……ありがとう。伝えてくれて、うれしいよ。」
その瞬間、教室の雰囲気が、あたたかい光に包まれたように感じた。
思い返せば、ずっと完璧でいようとしていた。
誰よりも正しく、誰よりも強く、誰よりも優れていなければいけない。
そう信じて、がんばっていた。
でも今は違う。
もう、完璧である必要はない。
比べられる必要もない。
誰かを見下す必要も、誰かに勝つ必要も。
わたしたちは、生きた人間。
正しさなんて、ひとつもない。
あるのは、ただそれぞれの“今を生きる姿”だけ。
授業のあと、ひとり教室に残ったわたしは、窓の外を見つめながら、心の中でふと思った。
――あの日、わたしの中の小さな子が、「いていいんだよ」って言ってくれた。
あの瞬間から、ようやくわたしは、“わたし”として生きはじめたのだ。
はじめての、素顔のわたしとして。
あとがき
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この物語は、どこかで誰かが体験したかもしれない、「心の旅」のひとつです。
けれどもし、あなたの中にも似たような想いが眠っていたなら――
それはきっと、あなた自身の物語でもあったのだと思います。
人は、いつからでも変わることができます。
遅すぎることは、決してありません。
ほんの小さな気づきや、誰かのやさしいまなざし。
それがきっかけで、心の奥にしまっていた“ほんとうの自分”が、そっと目を覚ましはじめます。
この物語が、あなた自身の“声なき声”に、そっと耳を傾けるきっかけになれたなら――
それ以上の喜びはありません。
あなたという存在が、この世界にいてくれて、ありがとうございます。
もしこの物語が心に響いたなら、
癒しを必要としている誰かに、そっと届けていただけたら嬉しいです。
